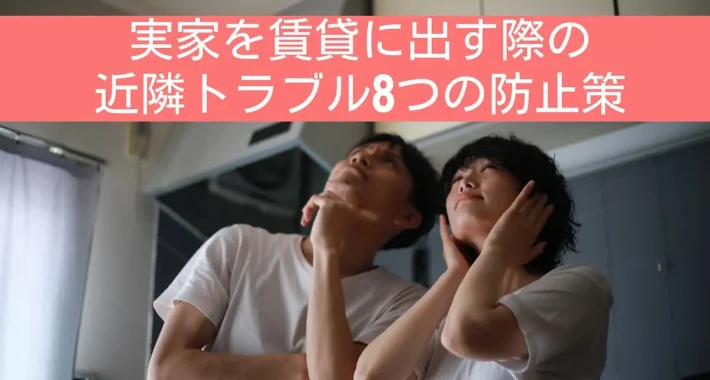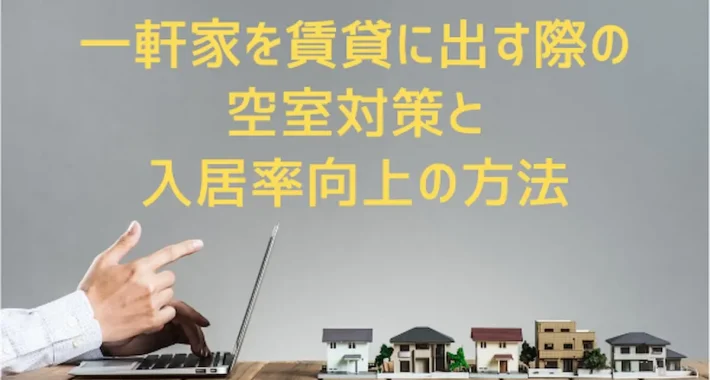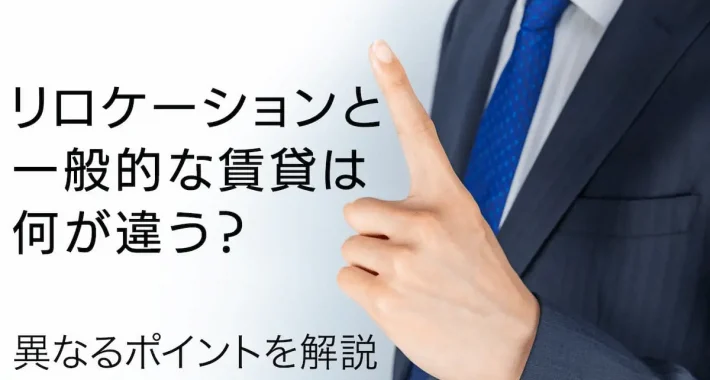自宅を賃貸に出すと、家賃収入により不動産所得が発生するため、確定申告が必要です。確定申告の際には、賃貸に出すにあたりかかった費用を収入から差し引いて所得を算出します。
自宅を賃貸に出すと、家賃収入により不動産所得が発生するため、確定申告が必要です。確定申告の際には、賃貸に出すにあたりかかった費用を収入から差し引いて所得を算出します。
この費用の一つとして「減価償却費」があります。
この記事では、「減価償却費」の考え方と確定申告時の計算方法について解説します。
私のお家、相場より高く貸せる?
今すぐ無料で賃料査定
目次
1. 減価償却費とは
減価償却費とは、建物や設備などの固定資産において、時間の経過とともに価値が減少することを考慮して、価値の減少分を費用として計上するものです。減価償却費の算出方法は税法によって定められており、耐用年数に応じて取得に要した費用のうち毎年一定額を費用計上します。
賃貸経営において、支出を伴う費用ではありませんが、費用計上することで不動産所得を抑えることができるため、節税効果が期待できます。なお、適用されるのは建物のみで、土地は対象外です。
2. 自宅を賃貸住宅にした場合の減価償却費の計算方法
減価償却費は、取得にかかった費用を税法によって定められた耐用年数に基づいて、価値の減少分として算出します。
耐用年数は建物の構造によって異なり、次の通りです。
| 構造(住宅用) | 耐用年数 |
|---|---|
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
47年 |
| れんが造、石造 ブロック造 |
38年 |
| 金属造(骨格材の肉厚4mm超) | 34年 |
| 金属造(骨格材の肉厚3mm超4mm未満) | 27年 |
| 金属造(骨格材の肉厚3mm以下) | 19年 |
| 木造 合成樹脂造 |
22年 |
| 木骨モルタル造 | 20年 |
なお、2007(平成19)年3月31日以前に取得した建物の減価償却の方法は算出方法が異なる場合がありますので、税務署にご確認ください。
自宅を賃貸住宅にした場合の減価償却費の計算において、自宅を新築で取得したのか、中古で取得したのかによって、耐用年数の算出方法が異なります。
下記の条件の建物について、新築/中古それぞれの場合を解説していきます。
・新築 2010(平成22)年4月1日
・建物の取得価額 1,000万円
・木造(住宅用)の法定耐用年数 22年 ⇒ 定額法の償却率 0.046
・賃貸住宅にした日 2024(令和6)年4月1日
2-1. 新築の場合
新築の場合は、法定耐用年数に基づいて計算します。
10,000,000円×0.046×9/12=345,000円
この事例では、貸出期間が9ヶ月のため、9/12としています。
参考:No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却[国税庁]
2-2. 中古の場合
・購入日 2015(平成22)年5月1日
※このほかの条件は新築と同様
中古で購入した物件の場合は、賃貸住宅にした後の耐用年数について、今後の使用可能期間を合理的に見積もることができれば、その見積年数を耐用年数として計算しますが、困難な場合には次のように簡便法にて計算します。
経過年数
2010(平成22)年4月1日から2015(平成27)年3月31日まで
⇒ 5年1か月 ⇒ 61か月
※経過年数には、2015(平成27)年3月31日から2024(令和6)年3月31日までの期間(購入時点~賃貸住宅にする前の期間)は含めない
購入時点での耐用年数(簡便法による耐用年数)
(264か月[法定耐用年数22年]-61か月[経過年数])+61か月[経過年数]×20%=215.2か月 ⇒ 17.93年 ⇒ 17年
※1年未満の端数の切捨ては、最後に行う
転用後の償却率(定額法)
17年 ⇒ 0.059
減価償却費の算出
10,000,000円×0.059×9/12=442,500
参考:No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却[国税庁]
3. 自宅を賃貸に出すと確定申告が必要

自宅を賃貸に出すと、家賃収入により不動産所得が発生するため、確定申告が必要となります。
会社員で給与所得を得ている方は、会社にて年末調整が行われるため、通常確定申告は不要です。しかし、家賃収入により不動産所得が発生した場合は、給与所得と不動産所得と合わせた金額に対して課税されるため、会社で年末調整を行っていたとしても、確定申告が必要となります。
なお、給与以外の所得が年間20万円未満の場合には確定申告は不要とされていますが、この措置は所得税のみが対象です。住民税は課税対象となるため、別途申告が必要なので注意しましょう。
4. 不動産所得の計算方法
不動産所得は、次の計算式で求められます。
不動産所得=収入-必要経費
ここからは、収入と必要経費の具体的な内容について、解説していきます。
4-1. 収入
次のようなものが収入として扱われます。
- 家賃
- 駐車場使用料
- 管理費・共益費
- 礼金
- 更新料
賃貸借契約時には入居者が敷金を支払うことがありますが、これは預り金として扱い、退去時に原状回復費用として受領する分のみが収入となります。ただし、敷引きなど事前に返金しないことが確定している部分については、返金しないことが確定した時点で収入として計上します。
4-2. 必要経費
賃貸経営の必要経費として計上できる費用は、次のようなものです。
- マンション管理組合へ支払う管理費・町内会費
- 修繕費・リフォーム代
- 賃貸管理会社への管理手数料
- 入居者募集にかかる広告宣伝費
- 物件運営のために使用した交通費
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険や地震保険料などの損害保険料
- 借入金の利息
- 減価償却費
- 司法書士や税理士に税管理を依頼した場合の専門家報酬
以上が必要経費にあたります。
なお、マンションの管理組合に支払う修繕積立金は下記の条件をすべて満たす場合にのみ、支払った年の費用に計上することが可能です。これに該当しない場合は、実際に修繕が実施された際に費用計上をします。
- 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
- 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
- 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
- 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
参考:賃貸の用に供するマンションの修繕積立金の取扱い[国税庁]
5.所得税の算出と確定申告の方法
不動産所得を算出したら、そのほかの所得と合算して所得税を算出し、確定申告を行います。
5-1. 所得税の計算方法
不動産所得は総合課税の対象です。給与などの収入がある場合は、これらを合算して課税所得金額を算出します。
課税所得金額=(給与所得+不動産所得+その他総合課税の対象所得)-所得控除
この課税所得金額に応じて、税率をかけて控除額を差し引き、所得税額を算出します。
所得税額=課税所得金額×税率-控除額
課税所得金額ごとの所得税率は次の通りです。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
参考:所得税の税率[国税庁]
5-2. 確定申告の方法
確定申告は、管轄の税務署に対して行います。
確定申告の流れ
- 確定申告書の作成
- 確定申告書の提出
- 納税・還付
確定申告で必要な書類
- 確定申告書※
- 収支内訳書※
- 青色申告決算書※(青色申告のみ)
- 本人確認書類
- マイナンバー
※国税庁のHPから入手、または確定申告作成コーナーにて入力
確定申告書の作成方法と提出
- 確定申告書作成コーナーで作成
- 確定申告ソフトで作成
- 規定のフォーマットにて手書きで作成
- 税理士に依頼する
①や②であれば、マイナンバーカードを用いてスマートフォンからe-Tax送信を行い、申告を完結させることが可能です。なお、マイナンバーの読み取りには、マイナポータルアプリおよび電子証明書のパスワードが必要です。
マイナンバーカードがない場合は、郵送か直接税務署へ提出することが一般的です。
青色申告特別控除とは
不動産所得の確定申告では、「白色申告」「青色申告」のいずれかを選択できます。
青色申告では下記の条件を満たすことで、65万円の控除が受けられるメリットがあります。
- 事業的規模(おおむね5棟10室以上)の賃貸経営であること
- 複式簿記による帳簿を用いること
- 貸借対照表と損益計算書を添付すること
- 期限内に申告すること
- e-Taxでの申告、または電子帳簿保存を行うこと
e-Taxでの申告、または電子帳簿保存を行うことのみが難しい場合は、55万円の控除となり、それ以外の条件を満たしていない場合は、10万円の控除となります。
これらの特別控除は黒字の範囲内でしか控除ができませんが、赤字の場合は3年繰り越しが可能です。
参考:青色申告制度[国税庁]
6. 減価償却費を費用計上することは節税に繋がる
減価償却費を適切に費用計上することは、不動産所得の圧縮に繋がり、節税が可能です。
減価償却費の算出方法は税法によって定められており、建物の構造によって減価償却費のもととなる耐用年数が、取得時に新築/中古どちらであったのかによって計算方法が異なります。
実際の支出を伴う費用ではありませんが、比較的大きな金額となり、節税に繋がりますので、忘れずに計上することが重要です。
カテゴリ: 家を貸す 関連記事
賃貸に役立つコラム記事
海外赴任時の賃貸に関して
転勤時の賃貸に関して
一戸建て・マンションの賃貸に関して
査定に関して
人気記事TOP5
タグ一覧

記事検索