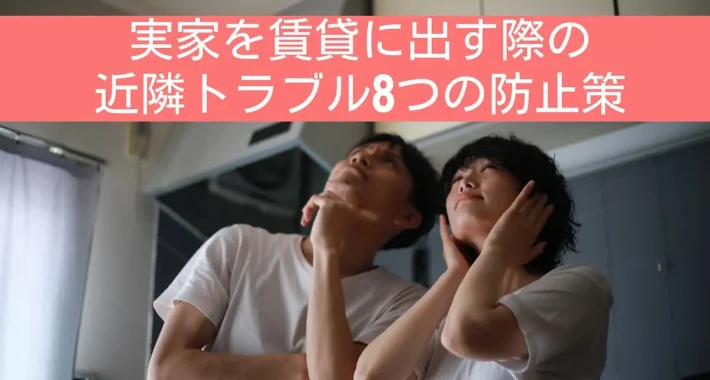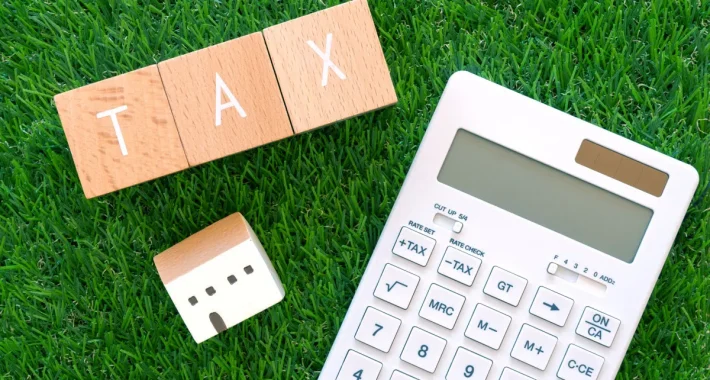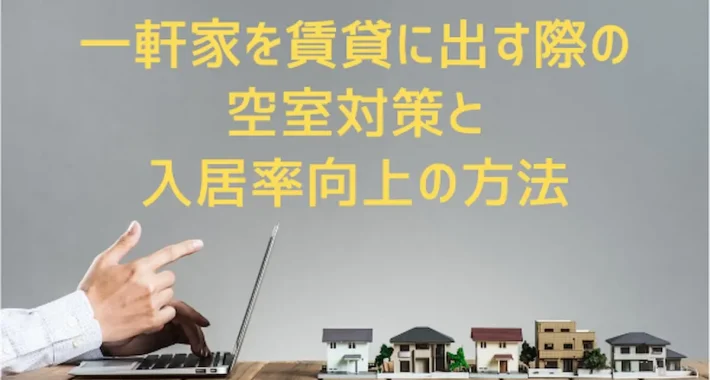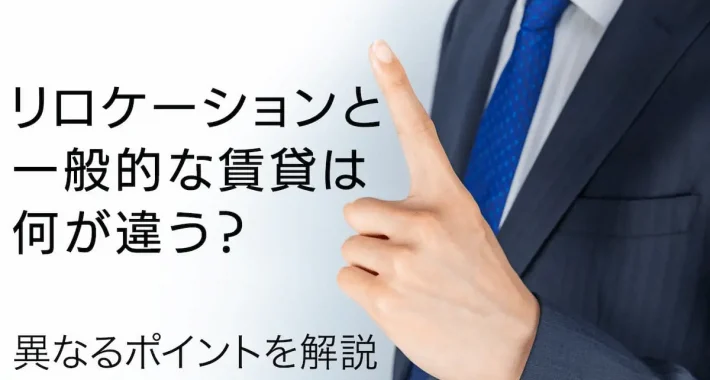家を貸す流れを知りたい!
海外転勤などが決まり、自宅を貸し出したいと考えているものの「具体的な準備や費用をはじめ、家を貸す流れが分からない」という方もいるのではないでしょうか。
家を貸す流れには6つのステップがあります。当記事ではこれらをポイントに絞って説明するのと合わせ、家を貸した後の流れも紹介することで家を貸す流れ全体がイメージしていただけるよう解説していきます。
私のお家、相場より高く貸せる?
今すぐ無料で賃料査定
目次
1. 家を貸す際の流れ6ステップとは

家を貸す際の流れ6ステップとは、以下のとおりです。
- 賃料査定を依頼する
- 賃貸管理会社を決める【選び方】
- 賃料と入居条件を決める
- 家を貸す準備をする
- 入居者の募集を行う
- 入居審査を行い賃貸借契約を結ぶ
それぞれ詳しく解説します。
1-1. 賃料査定を依頼する
家を貸す際には、実際にいくらで貸せるのか把握することからはじめます。
賃料査定には、概算賃料が分かる「机上査定」、詳細な賃料が分かる「訪問査定」の2種類があります。査定額は不動産会社によって異なるため、複数社に査定を依頼して比較することが大切です。査定を依頼する際は、一括査定サイトを活用するか、自ら不動産会社を調べて直接連絡します。
一括査定サイトは、一度に複数社に査定依頼を行えます。時間や手間が省けるので効率的な方法ですが、サイトによって参加している不動産会社が限定されたり、色々な不動産会社から連絡があるため、対応に時間を取られ各社の内容が分からなくなるなど注意が必要です。
相場に近い査定結果が知りたい場合は、物件の近くで営業している不動産会社や賃貸管理経験の豊富な不動産会社を個別に調べて依頼しましょう。それらの不動産会社なら、より現実的な査定額を提示してくれる可能性が高くなります。
また、最終的な査定額の確定には、実際に物件を見てもらう訪問査定が必要不可欠です。訪問査定では、物件の状態や周辺環境も細かくチェックしてもらえるため、机上査定だけでは分からない要素も含めてより正確な査定額を把握できます。
1-2. 賃貸管理会社を決める【選び方】
賃料査定を複数社に依頼したあとは、家を貸す際の管理を委託する会社を選定します。信頼できる賃貸管理会社を選ぶためには、以下のようなポイントに注目します。
- 管理実績や管理件数の多さ
- 管理委託に含まれる業務の範囲(入居者の募集業務・クレーム時の対応・更新や退去時の手続きなど)
- 独自のネットワークを活用した集客ルート
- 騒音等の入居者トラブルの対応
管理会社選びでは、管理実績や管理件数の多さなどに加えて、貸主に寄り添ったサービス内容や独自の入居者募集ルートがあるか、トラブル発生時の対応力などが重要なポイントです。貸主にとって、なるべく早く借主が見つかることは重要ですが、オーナーの状況に適したサービスを受けられるかも家を貸す際には大切です。
例えば、海外転勤が理由で貸し出す場合には、万が一のトラブル対応や退去時の手続きまでを対応してくれる会社に依頼するのが理想的でしょう。適切な管理会社が見つかったら、管理委託契約を締結します。
家を貸す際に信頼できる不動産会社選びのポイントは、以下の記事で詳しく解説しているので合わせてご覧ください。
関連記事
信頼できる不動産会社の選び方とポイント、家を貸すときは管理会社が重要!

1-3. 賃料と入居条件を決める
管理委託契約を締結したあとは、借主を募集するために賃料と入居条件を決めます。賃料は相場をもとにした査定結果を参考に決定するのが良いですが、希望額がある場合は管理会社の営業担当者に相談してみましょう。また、入居条件の項目には以下のようなものがあります。
- 賃貸借契約の種類(普通借家契約・定期借家契約・一時使用賃貸借契約)
- 敷金・礼金の金額設定
- 契約期間の設定
- 更新料の有無と金額
- 中途解約に関する条件
- ペット飼育の可否と条件
- 喫煙に関する制限
- 楽器演奏に関する制限
- 原状回復の範囲と費用負担
- 連帯保証人の要件
- 火災保険の加入義務 など
これらの条件設定は、厳しすぎると入居者が見つかりにくくなり、空室期間が長引くリスクがあります。
一方で条件が緩すぎると、賃貸契約終了時物件の価値低下や以下のようなトラブルの原因となる可能性があるので注意が必要です。
- 敷金が少なすぎることで、原状回復費用の未回収が発生する
- 厳密な禁止事項を定めないことで、騒音トラブルが起きる
- 原状回復費用の負担範囲を契約書で明確にしておかないことで、退去時にトラブルが発生する
家を貸すときの家賃の決め方については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
関連記事
家を貸すときの家賃の決め方を解説!重視される基準や算出方法について

1-4. 家を貸す準備をする
家を貸し出す前には、修繕やリフォーム・ハウスクリーニングなどを行い、入居者が快適に過ごせるように準備します。特にお風呂やトイレ、キッチンなどの水回りは汚れが目立ちやすい箇所なので、内覧時に好印象をもってもらうためにも必ずきれいにしておきましょう。
また、リフォームは賃貸管理会社と相談しながら進めることが重要です。設定する家賃や貸し出し期間によっては、リフォーム費用を回収できない可能性があります。特に転勤による一時的な貸し出しの場合は、費用対効果を慎重に見極める必要があるので、賃貸管理会社との打ち合わせが重要です。
1-5. 入居者の募集を行う
準備が整ったら、管理会社を通じて入居者の募集を開始します。募集活動は、不動産ポータルサイトや自社ホームページへの掲載が一般的です。なかにはグループ企業や提携している法人などの独自のネットワークを活用して集客を行うケースもあります。
このように、管理会社が募集活動を行うため、オーナー自身がやることはありません。また、入居希望者からの申し込みがあった場合は内見に対応しますが、内覧時の対応まですべて任せられる管理会社がおすすめです。
1-6. 入居審査を行い賃貸借契約を結ぶ
申し込みが入ったら、入居審査を行います。
入居審査とは、借主の支払い能力や連帯保証人の保証意思があるのかなど賃貸管理会社を通して保証会社が調査します。また、賃貸管理会社も物件案内時や電話応対などから人柄や態度もみています。
審査結果によっては申し込みを断る場合もありますが、契約後に賃料未払いや部屋で騒いだりなどの問題が起きてからでは遅いため、収入、人物の両面から家を貸して問題ない人物かしっかり審査してもらいましょう。審査に問題がなければ賃貸借契約の締結へと進みます。
海外転勤などで遠方にいる場合、電子契約などで契約を完了させることも可能です。
2. 家を貸した後の流れを解説

ここでは、実際に自宅を貸し出してから契約期間満了、退去後の原状回復費用の清算までを解説します。
2-1. 入居中の管理を行う
入居後の主な管理業務として以下のものが挙げられます。
- 室内設備の点検・管理(給湯器・エアコン・換気扇などの定期点検の手配や不具合対応)
- 家賃の管理や滞納時の督促
- トラブル対応
- 修繕工事の手配
トラブルは24時間365日発生する可能性があるので、管理会社にどこまで対応してもらえるかを必ず確認しておきます。
以下は家を貸した後に発生することが多い具体的なトラブル例です。
- 騒音等の生活音による近隣トラブルが発生する
- エアコンなどの設備が不具合を起こす
- 敷金の返還をめぐって揉める
- 無断でペットを飼育する
このようなトラブルを未然に防ぐには、入居審査を厳格に行うことや親族などの緊急連絡先を確認しておくことが重要です。また、保証会社の利用や転貸契約の締結も有効な対策となります。
2-2. 契約期間満了に伴う手続きを行う
契約期間が満了する前には、契約の更新や再契約、あるいは退去の手続きが必要となります。転勤からの帰国時期が決まっている場合は、その時期に合わせて解約手続きを進める必要があります。契約更新や再契約をせずに退去となる場合は、物件の明け渡し期日を明確に設定し、スムーズな引き渡しができるよう準備を進めます。
2-3. 退去後のチェックと原状回復費用の清算を行う
退去時には、入居前の状態と退去後の状態を確認・比較し、賃貸期間中に発生した損傷の有無をチェックします。入居者の過失によるものと認められる損傷については、原状回復費用として算出され、敷金から清算されることになります。
原状回復費用の清算が完了すれば、家を貸す一連の流れは終了です。
私のお家、相場より高く貸せる?
今すぐ無料で賃料査定
3. 家を貸す際の費用
家を貸す際に必要な費用は、以下のとおりです。
| 費用の種類 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 賃貸借契約を結ぶ際に貸主と借主の間に入る不動産仲介会社に対して支払う報酬 | 家賃1ヶ月分+消費税 ※リロの留守宅管理の場合は、仲介手数料の支払いはありません。 |
| 賃貸管理手数料 | 賃貸管理会社に管理業務を委託する場合に毎月支払う手数料 | 一般的な相場は家賃の5~10%前後 |
| リフォーム・クリーニング費用 | 物件の状態に応じて、入居者を集めやすくするために行うリフォームやクリーニング費用 | リフォームやクリーニングの内容に合わせて変動 |
| 原状回復費用の貸主負担分 | 賃貸物件の退去時に発生する、物件を借りた時の状態に戻すための費用 | 経年劣化や設備の老朽化によって変動 |
| 保険料 | 火災保険や施設賠償責任保険の費用 | 保険内容や保険会社によって変動 |
| 税金 | ・固定資産税および都市計画税 ・所得税および住民税 |
各税金によって算出方法が異なる |
関連記事
自宅を賃貸に出すメリット・デメリット14選!必要な費用・税金や具体的な手順も解説

4. 家を貸す流れで「一戸建て」と「マンション」の違いはあるのか
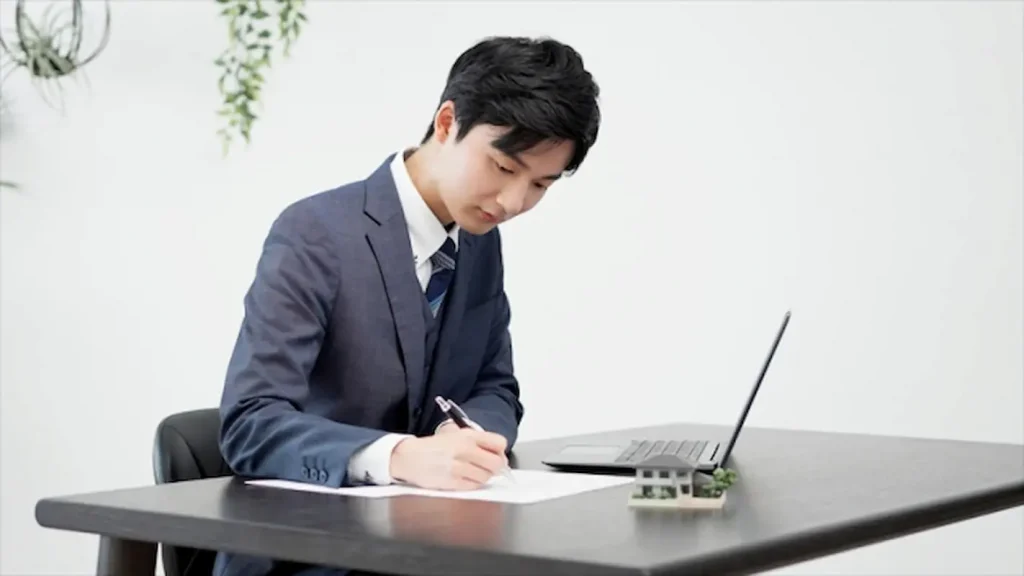
家を貸す流れで「一戸建て」と「マンション」による違いは、流れ全体ではありませんが、貸し出し条件の設定が一戸建ての場合は少し厳格になるでしょう。加えて一戸建てとマンションによって、家を貸す際に注意すべきポイントが異なるのでそれぞれの違いを解説します。
4-1. 一戸建てを貸す際の流れの違い
一戸建ては敷地と建物全体を貸し出すのに対し、マンションは基本的に一室を貸し出し、これに共有部分を利用できる権利がつくという点が違いになります。一戸建てでは日常的な庭の手入れや建物全体の維持管理(屋根・外壁の補修、雨樋・排水設備の点検、駐車場の舗装など)が必要になる点がマンションと異なります。そのため、家を貸す流れの中で「入居条件」を決める際、一戸建ての場合は入居者が行うべき管理範囲や費用負担を明確にしておくことが必要になります。例えば庭の除草剤の購入など日常的な管理は借主負担、外壁や屋根の修繕など経年劣化による修繕は貸主負担などです。場合により修繕費用も見積もっておくと良いでしょう。
また、戸建ては子どものいるファミリー層からの需要が高く入居者が限られます。
ファミリー層の入居者が重視するポイントは、学校までの距離や周辺環境の充実度などであり、エリアや立地によっては借り手探しに苦戦する可能性があります。そのため、戸建て賃貸の実績がある不動産会社に依頼し、賃料・貸し出し条件の設定や入居者探しを任せることが大切です。
関連記事
一軒家を貸すにはどうする?一戸建てを賃貸に出す方法と注意すべきポイントを解説

4-2. マンションの場合
マンションを貸し出す場合は管理規約に従う必要があり、賃貸すること自体に管理組合の承諾を求められるケースもあります。そのため、賃貸の可否に関する事前確認は必須です。また、賃貸できる場合には、管理規約の内容を借主に守ってもらう必要があります。もし借主が規約違反を犯した場合は、所有者が責任を追うのが一般的です。
マンションを貸す際の管理は居室やバルコニーのような専有部のみで、エントランスやエレベーターなどの共有スペースの管理は管理組合が行います。一戸建てと比べると管理しやすいのは、マンションのメリットでしょう。
一方で、借主が決まらずペットの飼育を限定して認めるなど条件変更をしようと思っても管理規約で禁止されていれば認めることはできないので自由度が下がるのはデメリットといえるでしょう。
一戸建てとマンションの違いを踏まえると、一戸建ては維持管理がマンションより増えるため貸し出し時の条件を少し細かくし、修繕に備えて費用を計画しておくこと、マンションは入居者も管理規約に従う必要があるため、賃貸条件の設定に注意することが重要です。
大きな違いはないですが、注意深くみると貸し出す流れの一部分で多少の違いがあり、注意すべきポイントが異なります。
関連記事
マンションを貸す際の注意点とは?流れや費用など賃貸管理会社が基礎知識を徹底解説

5. 転勤時に家を貸して賃貸運営を成功させる5つのコツ

転勤時に家を貸して賃貸運営を成功させるコツは、以下の5つです。
- 信頼できる管理会社の訪問査定を受ける
- 転勤の場合は一時使用賃貸借契約か定期借家契約を使う
- 一時的に貸す場合の管理方法は管理委託か転貸を選ぶ
- 確定申告を忘れずに行う
- 住宅ローンの有無によっては借り換えが必要になる
それぞれ詳しく解説していきます。
5-1. 信頼できる管理会社の訪問査定を受ける
信頼できる管理会社の訪問査定を受けることで、正確な賃料把握だけでなく、物件を高く貸し出すためのアドバイスや早期成約をするための助言なども得られます。また、具体的な収支シミュレーションを実施してもらうことで、貸し出し期間中の運営イメージを明確にできるでしょう。
さらに、サービスの説明を通して、管理会社独自の強みや営業担当者との相性を知ることができます。特に転勤という特別な事情を理解している管理会社では、遠方や時差のある海外で暮らす貸主の困りごとに対応でき、貸主専用アプリや安心保証サービスなどのサポート内容も充実しています。
このように、訪問査定を受けることで管理会社の対応力や信頼性、強み、営業担当者の相性などもわかるため、管理会社の選定が成功しやすくなります。
5-2. 転勤の場合は一時使用賃貸借契約か定期借家契約を使う
貸主と借主の両者で締結する賃貸借契約には、以下のように「普通借家契約」「定期借家契約」「一時使用賃貸借契約」の3つがあります。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | 一時使用賃貸借契約 | |
|---|---|---|---|
| 契約期間 | 基本的に1年以上の期間を設定 ※期間の定めのない契約も可 |
契約時に契約期間を設定 | 一時使用の目的を果たすまでの期間 |
| 契約の更新 | 可 | 不可 | 不可 |
| 貸主からの解約申し入れ | 正当事由がない限り不可 | 期間満了をもって解約可 ※期間満了の6ヶ月から1年前までの間に解約予告が必要 |
一時使用の目的を果たすことにより解約可 ※事前の解約予告が必要 解約日の3ヶ月前まで |
| 契約方法 | 口頭でも書面でも可 | 書面(または電磁的記録)でのみ可 | 口頭でも書面でも可 |
| 賃料 | 賃貸市場の相場 | 普通借家契約の8割ほど | 普通借家契約の8割ほど |
| 用途 | 投資や相続した空き家など(対象の家に住まず永続的に貸し出す) | 転勤など(対象の家に再入居する意向がある) | 転勤(対象の家に再入居する意向がある) |
このように転勤に則した「定期借家契約」または「一時使用賃貸借契約」を用いることが転勤時の賃貸運営を成功させるコツになります。
定期借家契約では期間満了の6ヶ月から1年前まで、一時使用賃貸借契約では解約日の3ヶ月前までに解約予告を行うことで契約を終了できます。
そのため、これらの契約であれば転勤からの帰任後にスムーズに再入居することが可能です。
また、一時使用賃貸借契約は「帰任」が解約の要件となるため、流動的な転勤によりフレキシブルに対応できる契約方法なのが特徴です。
一方、賃貸市場で一般的に用いられる普通借家契約は、更新を前提とした長期的な契約となるため、転勤のように期間を限定した貸し出しには不向きです。
定期借家契約と一時使用賃貸借契約の詳しい内容が気になる方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事
定期借家契約とは?メリットや注意点、他の契約との違いを解説

関連記事
一時使用賃貸借契約とは?リロケーションで使われる転勤者におすすめの契約方法

5-3. 一時的に貸す場合の管理方法は管理委託か転貸を選ぶ
自宅を賃貸する際の管理方法は、大きく以下の3つに分けられます。
| 自主管理 | 管理委託 | 転貸(サブリース) | |
|---|---|---|---|
| メリット |
・管理委託手数料がかからない ・入居者とコミュニケーションを取りやすい |
・管理を不動産会社に任せられる ・空室対策やクレームに関するアドバイスを受けられる |
・管理を不動産会社に一任できる ・家賃保証サービスを受けられるケースもある |
| デメリット | ・管理全般を行うため、手間と時間がかかる ・管理不十分によるトラブルが発生するおそれがある |
・管理委託手数料がかかる ・管理会社によってはトラブルが頻発する ・会社によって管理委託の範囲が異なる |
・管理委託手数料がかかる ・管理会社によってはトラブルが頻発する |
転勤のように遠方に引っ越す場合や本業が忙しい場合など、ほぼ全ての賃貸管理業務を管理会社に任せたい場合は「管理委託」または「転貸」を選択しましょう。管理委託は、入居者の募集や契約の締結、退去時の立会いなどの管理業務を管理会社が代わってくれるため、遠方にいる場合でも賃貸経営が可能です。ただし、会社によって管理委託の範囲が異なるため、どこまで対応してくれるのかを事前に把握しておく必要があります。
転貸は、いわゆる「又貸し契約」のことです。最初に物件オーナーと管理会社が賃貸借契約を結び、それから管理会社と入居者で契約を締結します。転貸の場合は、管理業務やトラブル対応までほとんどを任せられるので転勤などの方におすすめです。
「リロの留守宅管理」では、40年以上の賃貸管理実績を活かし、最も手間が軽減できる「転貸」方式を採用しています。丁寧なサポート体制も整っているので、家を貸すことを検討している場合は、気軽にご相談ください。
関連記事
委託管理とは賃貸物件の管理業務を代行してもらうこと!業務内容とメリット・注意点を解説

関連記事
サブリース契約ってどんな仕組み?サブリース契約のメリットやデメリットもご紹介
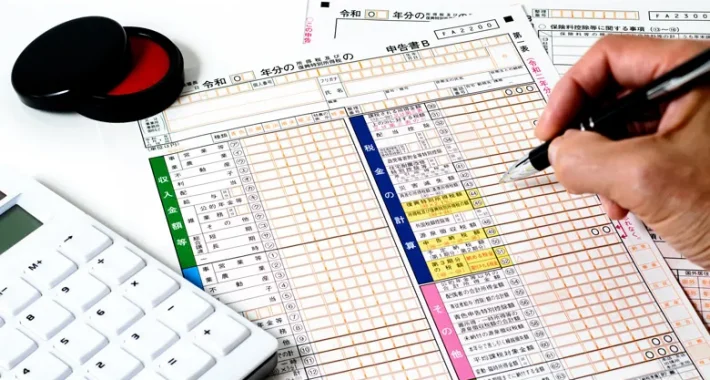
5-4. 税金の知識を身につける
賃貸運営を成功させるために、税金の知識を身につけたり節税の意識を高めたりすることが大切です。例えば、不動産所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は必須ではありませんが、申告することに意味があります。同一年で得た各所得の利益と損失を合算する「損益通算」を行うことが可能で、住民税などの節税につながります。
また、節税のためには些細な経費でも計上を忘れないために、領収書を紛失しないように管理することが大切です。海外赴任で確定申告ができない場合は、親族や税理士に「納税管理人」を依頼する必要があります。一部の賃貸管理会社では「確定申告サポートサービス」を提供しており、管理会社に納税管理人として対応してもらえます。
確定申告や税金に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事
持ち家を賃貸に出したときの確定申告や税金、計算方法と申告方法を解説

5-5. 住宅ローンの有無によっては借り換えが必要になる
住宅ローンは契約者が居住することを前提としているため、返済期間中は基本的に家を貸し出せません。無断で賃貸した場合、契約違反としてローン残債の一括返済を求められる可能性があります。
ただし、転勤等のやむを得ない事情による場合は、例外的に賃貸が認められることもあります。契約書を確認し融資先の金融機関に相談してみましょう。仮に契約書で認められていても金融機関に黙って家を貸し出すのは禁止されています。
金融機関の規定により異なるため、住宅ローンから不動産投資ローンへの借り換えによって賃貸が可能になることもあります。融資先の金融機関に相談してみましょう。
私のお家、相場より高く貸せる?
今すぐ無料で賃料査定
6. まとめ
家を貸す際の流れを把握することで、最初にやるべきことや借主が見つかるまでの具体的なイメージを膨らませることが可能です。特に賃料査定で信頼のおける管理会社に出会えるかどうかが、賃貸経営を成功させるポイントです。海外転勤を控えている方は、本記事で紹介した家を貸す流れや転勤時の賃貸運営を成功させるポイントを参考に、自宅の貸し出しを進めてみてください。
「リロの留守宅管理」は、40年以上の賃貸管理事業を持ち、今までに25万件以上の管理戸数実績があります。また、入居者募集・入居中・入居者退去にいたるまで、安心・安全にこだわった賃貸管理サービスを提供し、賃貸不動産経営のリスクに備えるさまざまな保証サービスでオーナー様をお守りいたします。無料の賃料査定を行なっていますので、賃貸経営をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆者
カテゴリ: 家を貸す 関連記事
賃貸に役立つコラム記事
海外赴任時の賃貸に関して
転勤時の賃貸に関して
一戸建て・マンションの賃貸に関して
査定に関して
人気記事TOP5
タグ一覧

記事検索